不動産投資は、安定した家賃収入や資産形成を目的に取り組む人が増えていますが、その一方で見落とされがちなのが「税金対策」です。
「どの税金がかかるのか」「どこまで経費にできるのか」「節税のために何をすべきか」——こうした疑問を持つ投資家は少なくありません。
本記事では、不動産投資を行う上で必ず知っておくべき税金の基本と節税テクニックを、具体例を交えて解説します。
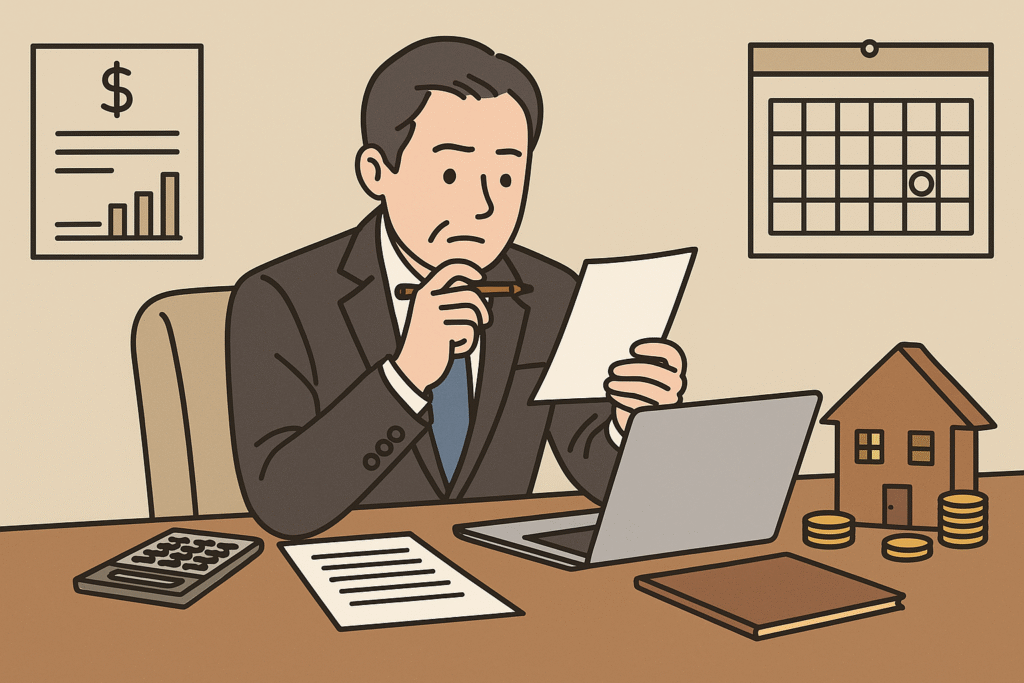
1. 不動産投資でかかる税金の種類
不動産投資では、以下のような税金が発生します。
① 所得税・住民税
不動産収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に課税されます。所得税は累進課税制度で、所得が増えるほど税率が上がる仕組みです。住民税は一律10%が目安です。
② 固定資産税・都市計画税
不動産を所有している限り毎年課税される税金です。固定資産評価額に応じて計算され、都市計画区域内の場合は都市計画税も追加されます。
③ 不動産取得税
物件を購入した際に一度だけ課税される税金で、固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出します。
④ 譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合に課税されます。所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」と、5年以下の「短期譲渡所得」では税率が大きく異なります。
👉 詳細は国税庁公式サイトをご確認ください:国税庁|不動産に関する税金
2. 不動産所得の計算方法と経費にできる項目
不動産投資における「節税」の鍵は、いかに経費を正しく計上するかにあります。
不動産所得は次の式で計算します。
不動産所得 = 家賃収入 – 必要経費
経費として計上できる主な項目
- 減価償却費:建物部分を耐用年数に応じて毎年費用化できる
- 修繕費:原状回復や設備交換のための支出(資産価値を大きく高めるリノベーションは資本的支出扱いになるので注意)
- 管理費・委託費:管理会社への委託料
- ローン利息:元本は経費にできませんが、利息部分は経費算入可能
- 固定資産税・都市計画税:毎年の税負担も経費計上できる
- 広告費・仲介手数料:入居者募集のための費用
- 交通費・通信費:物件管理のための出張や連絡に要した費用
こうした経費を漏れなく計上することで、課税所得を抑えられ、節税につながります。
3. 効果的な節税テクニック
① 減価償却費を活用する
減価償却は不動産投資における最大の節税メリットです。建物の購入価格を耐用年数に分割して費用化できるため、キャッシュアウトを伴わずに所得を圧縮できます。特に木造アパートは耐用年数が短く、初期の節税効果が大きいのが特徴です。
② 青色申告で65万円控除を受ける
不動産所得がある場合、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられます。また、赤字が出た場合には他の所得と損益通算が可能となり、給与所得者にとって大きな節税効果をもたらします。
③ 家族への給与支払い(事業的規模の場合)
一定の規模で賃貸経営を行っている場合、家族に給与を支払い経費化することも可能です。ただし、適正額や就労実態が必要となるため、税理士と相談の上で行うことが推奨されます。
④ 長期保有による譲渡税率の軽減
売却時の税金は、5年を超えると「長期譲渡所得」となり税率が大幅に下がります。節税の観点からも、物件の保有期間を戦略的に考えることが重要です。
4. 注意すべきポイント
- 節税を目的とした過度な経費計上は税務調査で否認されるリスクあり
- 減価償却費の計上は将来の売却益(譲渡所得)に影響するため、中長期的な税務戦略が必要
- 事業規模によっては「事業税」の課税対象になるケースもある
👉 実務的な節税相談は税理士への確認が必須です。
まとめ
不動産投資における税金は複雑ですが、基本を押さえ、経費を正しく計上することで大きな節税効果を得られます。
特に 「減価償却」「青色申告」「長期保有戦略」 は、投資家が必ず知っておくべき節税の三本柱といえるでしょう。
不動産投資は単に家賃収入を得るだけでなく、税務戦略を組み込むことで手取り収益を最大化できる投資手法です。これから不動産投資を始める方も、すでに所有している方も、節税の視点を持って資産形成を進めていきましょう。
関連記事・参考リンク
📩 不動産投資・節税対策に関するご相談はお気軽に
👉 株式会社L不動産 お問い合わせフォーム
株式会社L不動産
代表取締役 生田 忠士


コメントを残す