不動産投資の世界では、「立地」「利回り」「需要」が成功を分ける大きな要因です。しかし近年、通常の物件よりも安価で購入できる「事故物件投資」に注目が集まっています。
事故物件とは、自殺・殺人・火災・孤独死などが発生した「心理的瑕疵(かし)」のある不動産を指します。かつては敬遠される存在でしたが、地価高騰や利回り確保の難しさを背景に、投資対象として見直されているのです。
本記事では、事故物件投資が注目される理由、心理的要因や法制度の変化、投資する際のポイントを解説します。
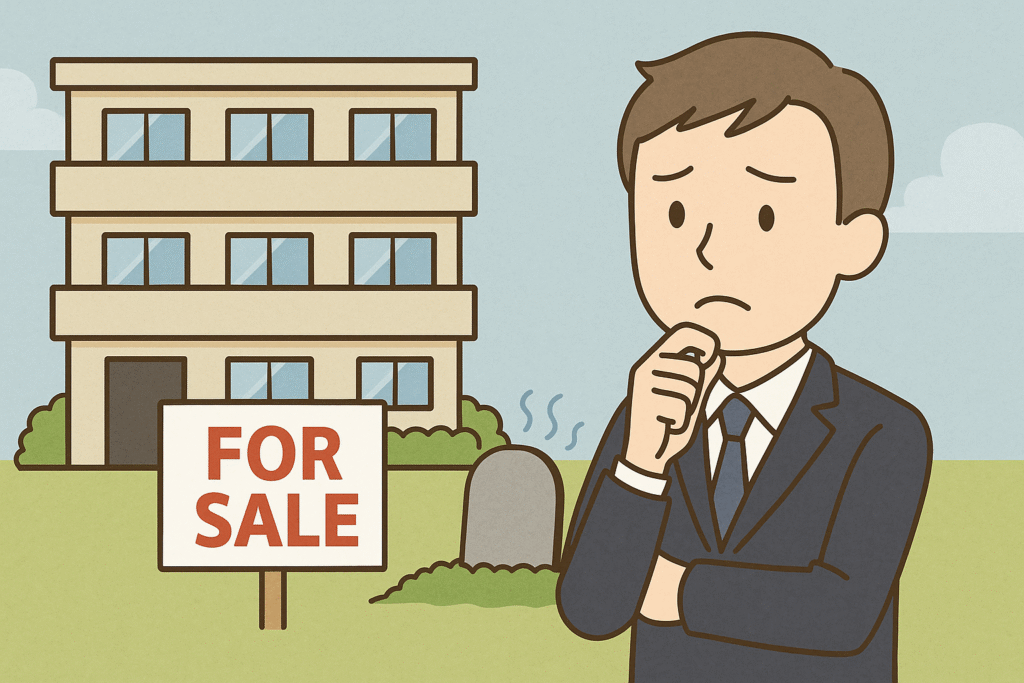
1. なぜ事故物件が投資対象になるのか?
① 相場より安く買える
事故物件は通常の相場より2〜5割安く売り出されるケースがあります。
例えば、都内で2,500万円相当のワンルームが「事故物件」として1,800万円で購入できることも。初期投資を抑えられるため、表面利回りが高くなるのが大きな魅力です。
② 賃貸需要は一定数ある
意外にも「家賃が安ければ気にしない」という入居希望者は少なくありません。特に単身者や外国人留学生などは価格重視の傾向が強いため、通常の相場より低く設定すれば入居者は見つかりやすいのです。
③ 市場価格上昇の波及効果
日本の不動産価格は近年上昇を続けています。2025年には東京23区マンション価格が前年比で10%以上上昇したとの報道もあり、投資家は「通常物件は高すぎる」と判断し、事故物件に目を向け始めています【参考:Reuters】。
2. 事故物件に対する心理的要因
事故物件は「安い」と分かっていても、多くの人は無意識に抵抗を覚えます。これは心理的瑕疵と呼ばれ、法的には「取引に影響する心理的要素」とされています。
ただし、最近では次のような動きがあり、心理的抵抗を減らす工夫も進んでいます。
- リノベーションやお祓いを行い、「清浄感」をアピール
- 事故物件専門のポータルサイト(例:大島てる)で情報公開が進み、透明性が高まっている
- 「安さを取る」層の存在により、一定の需要が発生
つまり、心理的要因は残るものの、情報の開示と受容層の拡大によって投資対象として成立しやすくなってきたのです。
3. 法制度と告知義務の変化
2021年に国土交通省が「事故物件に関するガイドライン」を公表し、告知義務の範囲が明確化されました。
- 自然死・日常生活中の不慮の事故(転倒など) → 原則、告知不要
- 自殺・殺人・火災・孤独死(遺体の発見が遅れた場合) → 一定期間は告知義務あり
- 期間の目安:おおむね3年間経過すれば告知不要とされるケースが多い
このルールにより、「いつまで事故物件扱いされるのか」という曖昧さが軽減され、投資家にとってリスクが見極めやすくなりました。
👉 詳細:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死に関する告知に関するガイドライン」
4. 投資で成功するためのポイント
事故物件投資には独特のリスクがありますが、工夫次第で安定した収益を確保できます。
① 入居ターゲットを明確に
「気にしない層」をターゲットに設定することが大切です。
例:家賃重視の若年層、外国人労働者、学生など。
② リノベーションでイメージ刷新
事故があった部屋だけでなく、共用部も含めてリフォームすると印象が大きく変わります。新築風の内装にすることで心理的抵抗を下げられます。
③ エリア選定は需要重視
「都心や大学周辺など需要が強いエリア」では事故物件でも入居者が見つかりやすいですが、人口減少地域では安さを武器にしても厳しい場合があります。
④ 売却出口を考えておく
3年以上経過すると「事故物件」の告知義務がなくなる場合が多いため、中期的に保有→売却を戦略に組み込むことも有効です。
まとめ:事故物件投資は「リスク管理」と「需要戦略」が鍵
事故物件は、通常の不動産投資に比べてリスクが高い反面、安く購入でき利回りを高めやすい投資手法です。
重要なのは、
- 表面利回りの数字だけでなく、実際の入居需要を見極めること
- 法制度や告知義務を理解し、出口戦略を持つこと
- 心理的瑕疵をどう緩和するかを工夫すること
こうした視点を持つことで、事故物件投資は単なる「怖い投資」から「チャンスのある投資」へと変わります。
関連記事・参考リンク
▶︎ 公式ブログ一覧はこちら
――――――――――――――――
株式会社L不動産
代表取締役 生田 忠士
https://leading-co.com
――――――――――――――――


コメントを残す